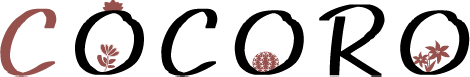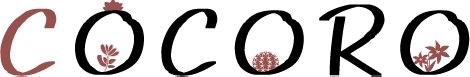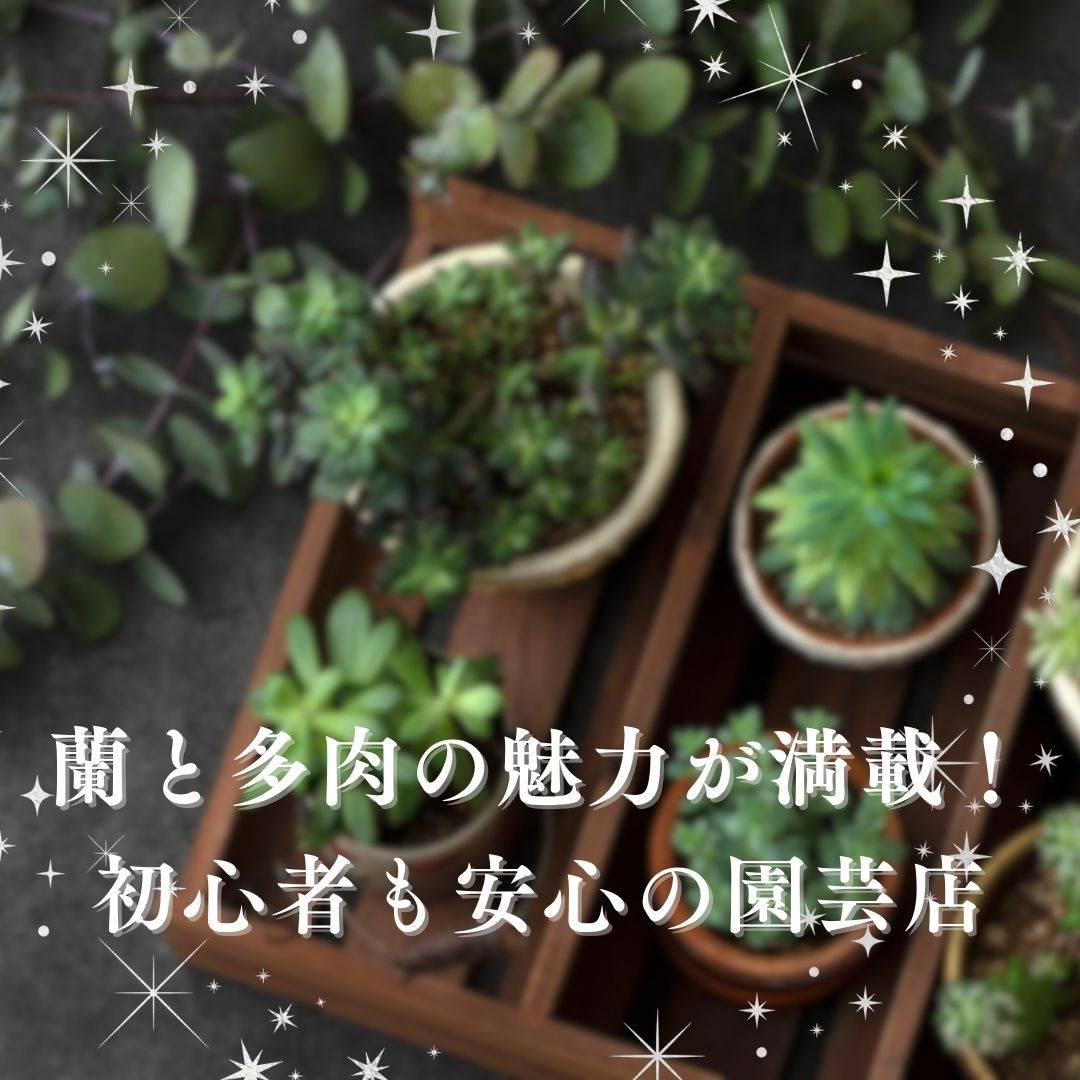失敗しない 蘭の冬支度と管理の秘訣(種類別の最適温度を解説)
2025/10/08
秋も深まり、朝晩の空気がひんやりとしてきましたね。 この時期になると、蘭を育てているお客様から最も多くいただくご質問が、「いつ、どうやって蘭を冬越しさせればいいですか」というものです。 蘭が次の成長期を元気に迎えるためには、この10月からの準備が非常に大切になります。 今回は、蘭の生育サイクルを考慮した、失敗を防ぐための「冬支度の3つのポイント」を詳しくご紹介します。 【基本のポイント】 10月からの冬支度3か条 ここでご紹介するのは、一般的なポイントです。 この3点を守るだけで、冬越し失敗のリスクは格段に減ります。 ポイント1:水やりは「乾燥気味」に大きく切り替える 蘭の成長が緩やかになる時期です。水を与えすぎると、株が水分を吸収しきれず、根腐れを起こす最大の原因となります。根腐れを防ぐため、乾燥気味を意識してください。 早朝や夜間の水やりは避け、午前中の温かい時間帯に済ませましょう。 ポイント2:肥料」は完全にストップ 次の成長期まで休ませる 肥料を与えると、かえって株が疲れてしまいます。固形肥料もこの時期までに必ず取り除き、次の成長期までお休みさせましょう。 ポイント3:蘭の置き場所は「種類別の最適温度」を意識して調整 蘭は種類によって耐えられる最低温度が大きく異なります。 ご自身の蘭がどのグループに属するかをチェックし、適切な時期に取りこむようにしましょう。| 蘭のグループ | 主な品種例 | 最低温度の目安 (これを目安に室内へ) | |---|---|---| | 高温性蘭 | 胡蝶蘭、カトレアの一部、バンダなど | 15℃を下回る前<br>(特に寒さに敏感な種類は18℃を目安に取り込むのが安全です) | | 中温性蘭 | デンドロビウム、一部シンビジウム、オンシジウムなど | 10℃〜12℃を下回る前 | | 低温性蘭 | シンビジウム、パフィオペディルムの一部など | 5℃〜10℃(低温で花芽がつく種類が多い) | 【種類別深掘り】翌年の開花を左右する冬の管理法 種類ごとに冬越しで目指す目的が異なります。 それぞれの特性を理解した管理で、失敗なく冬を乗り越えましょう。 A. 低温性蘭(シンビジウム、デンドロビウムなど)の管理 このグループは、冬の低温に当たる期間が必要な品種が多く、花芽の形成に寒さが欠かせません。 適度な寒さ: 室内でも暖房の入らない涼しい場所(玄関など)に置き、最低温度を5℃〜10℃で管理しましょう。シンビジウムは特に5℃ぐらいの低温に当てることが理想です。暖かい部屋に入れると、花芽が形成されない原因になります。 日光の確保 日中は、低温下でもしっかりと日光に当ててください。 寒さに当てつつ光合成を促すことが、丈夫な株を作る秘訣です。 水は厳しく:水やりを控えめにすることで、株が寒さに耐える力を高めます。 乾燥気味を意識してください。 B. 高温性・中温性蘭(胡蝶蘭、カトレアなど)の管理 このグループは、低温に弱い種類があります。 窓からの冷気対策(特に胡蝶蘭やデンファレなど)日中、日当たりを求めて窓辺に置くのは良いのですが、夜間は窓ガラスからの冷気(放射冷却)が直接当たらないよう、鉢を移動させましょう。 簡易的にダンボールで覆うだけでも保温効果があります。 暖房と湿度:暖房を使用している室内は乾燥しています。霧吹きで葉水(はみず)を小まめに行い、葉の乾燥を防いでください。 暖房の風: 暖房の温風が直接当たると、乾燥により葉が傷みますむことがあるので、注意が必要です。 まとめ:冬の管理を成功させるために 蘭の冬越し成功の鍵は、「気温を確認しながら適切な対処をすること」と「乾燥気味に管理すること」の2点に尽きます。 特に、最低温度を守ることは、株を健康的に育てるための重要なポイントです。 ご自宅の蘭の種類と耐寒性を把握し、適切なタイミングで室内に取りこむか寒さ対策をしてください。 これらのポイントをおさえれば、あなたの蘭もきっと元気に春を迎えてくれるでしょう。
----------------------------------------------------------------------
COCORO
大阪府藤井寺市岡1丁目
電話番号 : 090-5672-2583
----------------------------------------------------------------------